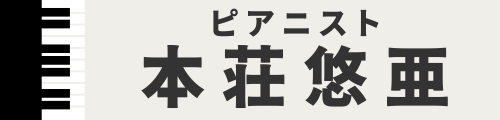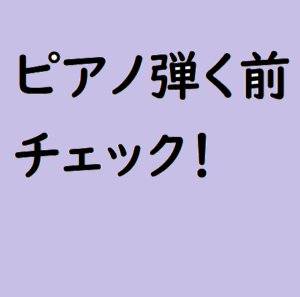練木繁夫先生の「幽玄な音」に接して
かなり久しぶりのブログ更新になる。この公式サイトも近々リニューアル予定なので、楽しみにお待ちください。
先日、とやま室内楽フェスティバルというマスタークラスに参加し、レッスンとコンサート出演を終えてきた。
そこで桐朋の大学院でもお世話になっている練木繁夫先生から、直接教えを乞うことができた。
練木先生のレッスンは哲学的で詩的で、一瞬で虜になったのだが、先生の演奏はさらに衝撃的なものだった。
今回一番の収穫になったのが、練木先生の室内楽の本番の実演を、譜めくり担当の特権としてごく間近で「見て」、「聴く」ことができたことだった。
練木先生の演奏にはじめて対峙したとき、こんな感想を持った。
「こんなにピアノを『弾かなくて』いいんだ。」
そして、次の瞬間にはこのように感じた。
「こんな音だって出していいんだ。」
練木先生は言うまでもなく室内楽の名手であるが、その演奏は予想とは大きくかけ離れたものだった。
室内楽の名手とあらば、きっちりと準備され、寸分の狂いもなく、息ぴったりに弦楽器奏者たちと合わせるのだ、と僕は予想していたのだった。
先生はピアノの鍵盤を弾くのではなく、まるでフワフワと浮いており、たまたまそこに鍵盤があったかのような手つきだった。
まるで打鍵していることを隠しているかのように。
そしてピアノを「弾く」というそぶりは全くせず、ゆったりと呼吸し、ただそこに「在った」のだ。
先生の音はある意味では薄い、しかしまろやかな音だった。
正直、ピアニストが座っている位置で聴こえる音の圧力は、拍子抜けするほどに少なかったのだ。
あまりにも音が空気主体なものだったから、本当にこれでクインテットを支えられるのか、傍から不安になったほどだ。
ブラームスの弦楽五重奏曲のいちばん熱情的な部分であってさえ、ピアノを弦楽器のひとつのように扱い、そして彼らと一緒に「在った」。
でもその弦楽器は大きくて弦楽器奏者たちを包み込むようだから、それに抱きかかえられた弦楽器たちは嬉しそうに歌う。
その様子を見て、私はこれまでの自分が間違っていたことを恥じた。
ピアノを弾くということは、つまりこういう風に打鍵してこういう音を出すのだ、と思い込んでいたのはすべて自分だったのだ。
そうしないと安心できないがために、知らず知らずのうちに慣れ親しんだ「安心」の音に安住していたのだ。
芯のあるボディのある音が出せれば、不安な舞台の上でも少しは気持ちが和らぐだろう。しかしこれでは自分のために演奏しているだけ、自己満足でしかない。
出している奏者が不安に感じるほど幽玄な、空気だけの音、それを確信をもって出せてこそピアニストなのだ。
今回の練木先生の演奏に出会ってから、何度も自分の手でその音を出してみようと、物まねをした。
1か月ほどたって、ようやくそれらしい振る舞いができてきたように思う。結局のところ、本当に変わりたければ、意識ごと体ごと作り変える必要があるのだ。小手先ではだめだ。
よい実演との出会いは、レッスンの何倍も貴重な経験。
少なくとも私は、先日の50分間で数か月分のレッスンに匹敵する学びを得たと思う。
しかしそうやって、奇跡的な実演から学べるためには日々の観察眼があってこそ。普段から、これとこれは何が違うんだろう?と思いをはせているからこそ、優れたものに出会った際に驚きをもつことができる。
わずかな違いに目をつけ、何が違うのだろう?と千思万考すること以外に道はないだろう。